静かな場所にいても「キーン」「ジー」「ゴー」といった音が耳の中で鳴っているように感じることはありませんか?
それは「耳鳴り」と呼ばれる症状です。多くの方が経験しますが、放置すると慢性化し、生活の質を下げることもあります。
今回は耳鳴りの仕組みや原因、種類、予防・改善のポイントについてご紹介します。
■ 耳鳴りとは?
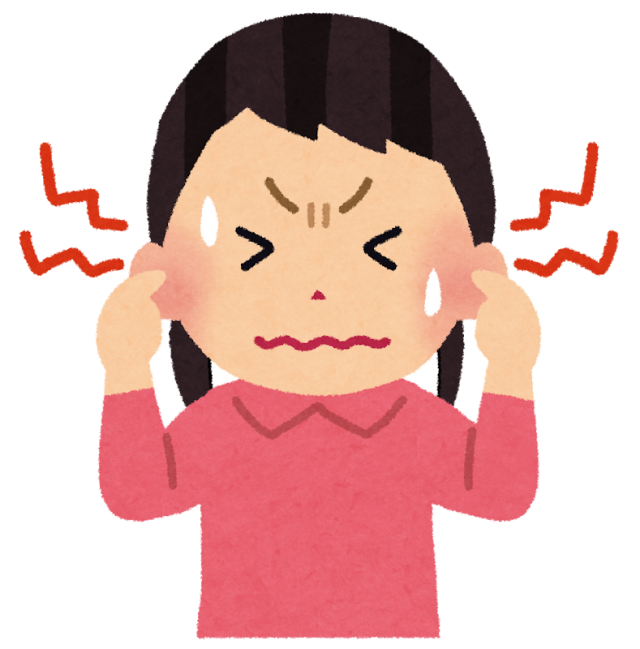
耳鳴りとは、外部から音がしていないのに耳の中で音を感じる状態のことをいいます。
「キーン」「ザー」「ボー」などの音が聞こえるのに、実際には何も鳴っていないというものです。
耳鳴りには、聴力低下を伴うタイプと聴力低下を伴わないタイプがあります。
たとえば、耳の検査をしても聴力に異常がないのに耳鳴りだけが続く方も少なくありません。これは、ストレスや自律神経の乱れ、筋肉の緊張によって起こるケースが多いです。
一時的なものもありますが、長く続くと集中力の低下や不眠、イライラなどを引き起こすこともあり、早めのケアが大切です。
■ 耳鳴りの原因
耳鳴りの主な原因は、内耳の血流障害や神経の過敏反応、自律神経の乱れといわれています。
特に、次のような要因が関係します。
-
ストレスや過労:自律神経が乱れ、内耳への血流が低下して神経が過敏になります。
-
睡眠不足・緊張状態:脳が休まらず、聴覚神経が過剰に働いたままになります。
-
肩こり・首こり:筋肉のこわばりで耳への血流が妨げられ、耳鳴りを悪化させます。
-
加齢や耳の老化:内耳の感覚細胞が弱まり、音信号が正しく伝わらなくなることも。
-
騒音・イヤホンの多用:長時間の音刺激により聴覚神経が疲労し、耳鳴りを起こします。
耳鳴りは「耳だけの問題」ではなく、全身の血流や神経バランスの乱れが関係しているのです。
■ 予防・改善方法
耳鳴りを防ぎ、軽減するためのポイントは次のとおりです。
-
十分な休息・睡眠をとる:脳と神経の興奮を鎮め、リセットすることが大切です。
-
ストレスをためない:深呼吸やストレッチ、趣味などでリラックス時間をつくりましょう。
-
首・肩のケア:温めたり、軽い運動で血流を促進し、耳への循環を整えます。
-
冷え対策・血行改善:入浴や温かい食事で体を冷やさないようにしましょう。
-
音の刺激を減らす:イヤホン・ヘッドホンの長時間使用を避け、耳を休ませる時間を。
はりきゅうルーム岳では、耳鳴りに対して鍼灸などによりで血流と自律神経を整える施術を行っています。
首・肩の緊張をほぐし、内耳への循環を改善することで、聴力低下を伴わない耳鳴りにも効果的です。

この記事に関する関連記事
- 40代女性 突発性難聴による耳鳴り・閉塞感を、顎の緊張解消により短期間で改善した症例
- 50代男性 耳管開放症による自声強調(自分の声が響く症状)と耳閉感の改善症例
- 50代男性 腎疾患による突発性難聴に伴う聴力低下・耳のつまり感の改善症例
- 40代男性 慢性上咽頭炎による全身倦怠感、関節痛、動悸の改善症例
- 50代男性 突発性難聴による重度の聴力低下を、発症直後の施術で早期に回復した症例
- 40代男性 ストレスが原因の突発性難聴による耳鳴り・聞こえづらさの改善症例
- 40代女性 ストレスによって再発した耳鳴りの改善症例
- 50代男性 突発性難聴が引き起こした耳鳴りの改善症例
- 80代男性 突発性難聴が引き起こした重度の耳鳴りの改善症例
- 耳管狭窄症と耳管開放症
- 耳管開放症とは・・・?
- 耳管狭窄症に効く薬はあるの?
- 耳管狭窄症とは?
- 耳鳴りに効く薬とは?
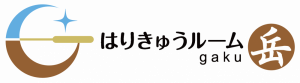










お電話ありがとうございます、
はりきゅうルーム岳 博多院でございます。