「自分の声が頭の中で響く」「耳が詰まったようなのに、抜けるような感じもある」「呼吸音が耳の中で聞こえる」──
このような違和感を感じたことはありませんか?
それは**耳管開放症(じかんかいほうしょう)**の可能性があります。
耳管とは、耳と鼻をつなぐ細い管で、普段は閉じていますが、あくびや飲み込みの動作で一時的に開き、耳の中の気圧を調整しています。
しかし、何らかの原因で耳管が常に開いたままになってしまうと、耳の中に空気が通りっぱなしになり、
「自声強調(自分の声が響く)」「こもり」「耳閉感」「呼吸音が聞こえる」といった不快な症状が現れます。
耳管狭窄症とは逆に、耳管が開きすぎることで起こるため、耳鼻科でも区別が重要です。
気圧の影響ではなく、日常生活の中での体調や環境変化が関係しているケースが多く見られます。
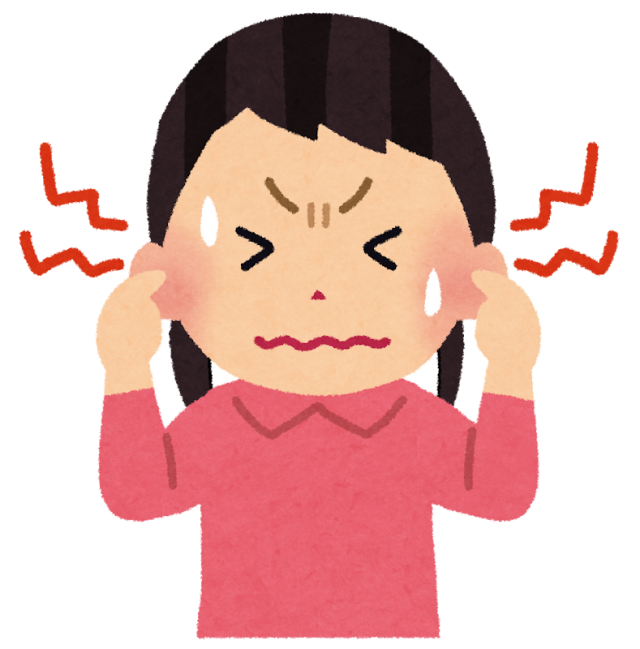
■ 原因
耳管開放症の主な原因は、体のバランスや生活習慣にあります。
-
急激な体重減少
ダイエットや病気などで体重が急に減ると、耳管まわりの脂肪組織が減少し、耳管を支える力が弱まってしまいます。 -
ホルモンバランスの変化
女性では妊娠や更年期など、ホルモンの変動によって耳管周囲の粘膜が薄くなり、開放しやすくなることがあります。 -
ストレス・疲労・脱水
自律神経の乱れや体内の水分不足も、耳管の開閉機能に影響を与えます。特に、睡眠不足や過度な緊張が続くと発症しやすくなります。 -
姿勢や筋肉のこり
首・肩・顎まわりの筋肉がこると、耳まわりの血流が悪化し、耳管の動きが不安定になります。
長時間のスマホ操作や猫背姿勢もリスクの一つです。
このように、耳管開放症は単なる耳の不調ではなく、全身の状態を反映するサインでもあります。
■ 一般的な治療法
耳鼻科での治療は、まず原因の特定と生活習慣の見直しから始まります。
体重減少が関係している場合は、適正体重への回復を目指します。
また、水分をしっかりとる・鼻うがいを控える・加湿を心がけるといったセルフケアも効果的です。
薬による治療では、粘膜の状態を改善する点鼻薬や、耳管を一時的に閉じる作用のあるホルモン剤・エストロゲン軟膏が使われることもあります。
重度の場合、耳管に空気の通りを調整する耳管ピン挿入術を行うこともあります。
一方で、耳周囲の筋肉や自律神経のバランスを整えるアプローチも注目されています。
特に、首・肩・顎まわりのこりをほぐし、血流を改善することで耳管の機能が安定しやすくなります。
ストレスや緊張が関係している方には、リラックス療法や鍼灸なども有効とされています。
■ まとめ
耳管開放症は、耳の異常というよりも「体のコンディションが崩れたサイン」です。
ストレスや生活習慣、姿勢の乱れが積み重なることで起こりやすく、再発を防ぐためには体全体のケアが欠かせません。
はりきゅうルーム岳では、耳まわりから首・肩・顎にかけての筋肉をやさしくゆるめ、自律神経と血流のバランスを整える施術を行っています。
薬では届かない“内側からの改善”を目指し、耳の機能を自然な状態へと導きます。
耳の違和感や自声の響きにお悩みの方は、ぜひ早めにご相談ください。
この記事に関する関連記事
- 40代女性 突発性難聴による耳鳴り・閉塞感を、顎の緊張解消により短期間で改善した症例
- 50代男性 耳管開放症による自声強調(自分の声が響く症状)と耳閉感の改善症例
- 50代男性 腎疾患による突発性難聴に伴う聴力低下・耳のつまり感の改善症例
- 40代男性 慢性上咽頭炎による全身倦怠感、関節痛、動悸の改善症例
- 50代男性 突発性難聴による重度の聴力低下を、発症直後の施術で早期に回復した症例
- 40代男性 ストレスが原因の突発性難聴による耳鳴り・聞こえづらさの改善症例
- 40代女性 ストレスによって再発した耳鳴りの改善症例
- 50代男性 突発性難聴が引き起こした耳鳴りの改善症例
- 80代男性 突発性難聴が引き起こした重度の耳鳴りの改善症例
- 耳管狭窄症と耳管開放症
- 耳管狭窄症に効く薬はあるの?
- 耳管狭窄症とは?
- 耳鳴りに効く薬とは?
- 耳鳴りの原因とは?
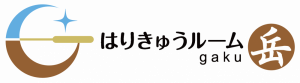










お電話ありがとうございます、
はりきゅうルーム岳 博多院でございます。